
Xシリーズ史上最高の高速性能を備えたFUJIFILM X-H2Sを使う人間ならどうしても気になってしまう存在が、APS-Cフォーマットとしては規格外とも言える4020万画素のXシリーズ史上最高画質を実現した兄弟機「X-H2」。
この記事を書いている2025年7月時点では、その後にX-T5、X-T50、そしてX-E5と4020万画素の高画素タイプのセンサーを搭載したXシリーズも充実してきた。レンズ固定式のX100シリーズも最新モデルのX100VIは4020万画素ということで、FUJIFILMの力を入れていく方向性がみえてきた。
例に漏れずX-H2Sを使っていてX-H2が気になり入手してしまった私の目線で、実写を交えてその魅力を紹介していきたいと思う。
X-H2はベースモデル、X-H2Sは派生モデル
X-H2/X-H2Sのネーミングを見て欲しい。双方の前のモデルは「X-H1」、そして高画素タイプのX-H2と高速タイプのX-H2Sという命名だ。各メーカーのカメラの名称は例えばSONY「α7」というベースとなるカメラの名称に対して、高画素タイプのものが出ると「α7R」といったように派生モデルに対して特徴を示すようなアルファベットを付け足すような命名がよく見受けられる。最近ではPanasonicのLUMIXシリーズでも同様なイメージだ。
にも関わらず、X-H2シリーズは高画素タイプが「X-H2」と名乗り、積層型CMOSセンサーを搭載した「X-H2S」が派生モデルのような命名となっている。(Leicaのフルサイズミラーレス一眼のSLシリーズも、似たようにベースモデルの高画素タイプSL3に、動画や高速性能に優れたSL3-Sというネーミングだ。たしかにLeica製品もレンジファインダーのMシリーズも含めて6100万画素がスタンダードになってきている。)
X-H2Sが先に登場したため少し違和感があったものの、X-H2が少し遅れて登場した際には、FUJIFILM Xシリーズは今後4020万画素がオーソドックスな仕様になっていくのでは…ということを予感させられた。ある意味その予感は的中したと言って良いと思う。
カメラ業界に身を置く人たちの中ではデジタルカメラは機械的な部品よりも、キーとなる電子部品の部品単価が実際の製品の販売価格に対してかなり支配的であることが共通の理解として存在している。イメージセンサーはまさにその代表格だ。
これまで10万円前後で魅力的な製品を送り出してきたFUJIFILM Xシリーズの製品価格が、その頃からするとかなり高価に感じられるが、世の中のカメラ製品で一般採用されていない4020万画素のイメージセンサーはかなり高価なデバイスであろうことが想像でき、事情を知るものとしては致し方ないのかなと思ったりもする。
話は戻って、4020万画素がオーソドックスな仕様となってきたということは、もちろん競合他社製品との差別化、Xシリーズの今後の提供価値を高めていくための選定であり、35ミリフルサイズ製品を持たないFUJIFILMならではの闘う方向性が見えてきたようで、1ユーザーとして頼もしく感じている。
見せてもらおうか、4020万画素の実力とやらを
- Camera: X-H2
- Focal length: 35mm
- Aperture: ƒ/1.2
- Shutter speed: 1/500s
- ISO: 320
X-H2を買って、どれだけ違うのかな…と思って撮影して驚いた1コマ。レンズはVoigrlander NOKTON 35mm F1.2である。画素数が多くなると、写真はどうなっていくか?拡大をしたときにどこまでも解像しているという満足感も一つ。プリントで引き伸ばしができる、トリミングの余裕が生まれるといったメリットもあるが、鑑賞サイズでみたときにはむしろ「ナチュラルさ」が際立つような印象を持っている。
カメラはレンズから入ってきたアナログの情報(光)を、カメラ内のデバイスの処理能力に応じたデジタルデータにコンバートしている。イメージセンサーや各種プロセッサーの能力は世代やかけられたコストによっても差がでるものだが、ある程度以上の性能を持っているものであれば、高画素であればある程より緻密にデジタルデータ化していると言える。
今、フィルムブームに続いて一部でオールドコンテジブームが到来したと言われ初めて久しいが、これは逆に「写り過ぎていない」そのファジーな感じが、肉眼で見た世界との大きなギャップとなり新鮮さを感じさせているとも考えられている。
つまり、より緻密な描写というのは、究極は我々が肉眼で見ている世界そのものであり、デジタルカメラの高精細な描写が向かう究極は、肉眼で見ているようなある意味ではナチュラルな世界、それこそ目の前に「本物」が存在すると錯覚するような描写ということになる。良い意味で「生っぽい」と表現されるこのナチュラルさが、高画素のカメラで撮った写真を鑑賞サイズでみたときに得られる美点ではないか。
加えて、レンズの個性でもあり極端すぎると弱点にもなり得る収差がより顕著に見えるようになってくるような印象も持っている。
上の写真で使ったVoigrlander NOKTON 35mm F1.2は、開放付近は球面収差によるフレアがかなり残っており、それがこのレンズの個性の一つになっている。X-H2SやX-Pro3で使用していたときよりもさらにその美しいフレアを感じることができて、「ああ、やっぱりX-H2は違うんだな…」と妙に納得させられたのをおぼえている。
- Camera: X-H2
- Focal length: 35mm
- Aperture: ƒ/1.2
- Shutter speed: 1/320s
- ISO: 500
子供を撮っていると、その純粋な瞳の輝きに生命力や愛おしさを感じる。瞳の輝きは、もちろん映り込む光源の力によるところや、目の表面の水分量などによっても左右されるところがあるが、開放付近でベールのような薄いフレア纏った描写のレンズでは、その輝きが瑞々しく描かれる。
軟かい描写はむしろ得意?
前項での話もふまえて、今のところは高精細な描写だけでなくむしろ軟かい描写もX-H2をはじめとした4020万画素Xシリーズの得意領域なのではないかと思っている。
- Camera: X-H2
- Focal length: 35mm
- Aperture: ƒ/1.2
- Shutter speed: 1/200s
- ISO: 1250
- Camera: X-H2
- Focal length: 23mm
- Aperture: ƒ/1.2
- Shutter speed: 1/1600s
- ISO: 640
最初は、Voigrlander NOKTON 35mm F1.2や23mm F1.2をはじめとしたx-mountレンズたちは、撮影体験を重視してX-Pro3専用レンズとして使い続けるつもりだった。それが、X-H2で撮影することでまた違う側面を見せてくれたのだから、本当にレンズ交換式カメラの世界は深い。
- Camera: X-H2
- Focal length: 35mm
- Aperture: ƒ/1.2
- Shutter speed: 1/2700s
- ISO: 640
- Camera: X-H2
- Focal length: 35mm
- Aperture: ƒ/1.2
- Shutter speed: 1/2700s
- ISO: 640
離れて暮らす娘の高校の入学式に行き、教室から撮った桜。年頃の娘はカメラを向けると嫌がるが、この日はめずらしく写真を褒められた。
- Camera: X-H2
- Focal length: 35mm
- Aperture: ƒ/1.4
- Shutter speed: 1/2900s
- ISO: 320
この日はものすごい強風に雨も降っていて、傘が何度もひっくり返ったのを思い出す。ぜひ高校では良き思い出をたくさん作って欲しいと願うばかり。
もちろん硬質なもの(ブツ撮りなど)も得意
仕事で深度合成が必要だったときに、試しにX-H2を使ってみたがフォーカスブラケット撮影ができるので大変に助かった。あとはPhotoshop上でレイヤーとして読み込んで画像を合成するだけ。
Photoshp上の操作はカメラのキタムラさんのShaShaのこちらの記事を参考にさせていただきました。
- Camera: X-H2
- Focal length: 50mm
- Aperture: ƒ/10
- Shutter speed: 1/160s
- ISO: 160
仕事の写真は貼れないので、X-H2で撮影したX-H2S(ややこしい)の写真を貼っておきます。これまで、カメラの物撮りで使うカメラはフルサイズ以上のフォーマットで、ローパスレスのものでないと表面のディテールが描ききれないように感じていましたが、X-H2は良い意味でAPS-C機とは思えない精細感が得られます。(ブログ掲載だと縮小の画質が良くなくて残念な感じに見えるかもしれないですが…)
また、USB-Cケーブルでのテザー撮影にも対応しており、カメラにUSB端子のクランプなども付属していて、仕事にも使えるカメラを使っているんだと高揚感を感じることができた。
自由作例
- Camera: X-H2
- Focal length: 23mm
- Aperture: ƒ/1.4
- Shutter speed: 1/640s
- ISO: 500
電車好きの子供が喜ぶようなスペシャルルームを備えたホテルに泊まったときのカット。最新のF1.4単焦点レンズらしく、木製のドクターイエローが浮かび上がるようなキレのある描写が嬉しい。
- Camera: X-H2
- Focal length: 23mm
- Aperture: ƒ/1.4
- Shutter speed: 1/800s
- ISO: 125
東池袋の近くにある、木製の遊具やおもちゃがあるキッズパークで遊んだときの写真。これまでのXシリーズは、背景のボケの質感があまり好ましくないときがあったが、木でできたボールがなかなかリッチな感じに描かれてると思う。
- Camera: X-H2
- Focal length: 23mm
- Aperture: ƒ/1.4
- Shutter speed: 1/900s
- ISO: 320
自転車の子供座席で寝てしまった息子。冬場寒いのでレインカバーで防寒しているので、ビニール越しの撮影。こういうときにハイライトやシャドーの描かれ方がすごく綺麗だと感じる。
- Camera: X-H2
- Focal length: 33mm
- Aperture: ƒ/1.4
- Shutter speed: 1/250s
- ISO: 125
夏場のカット。同じく自転車の子供座席にて、こちらはサイドは開けているので素通しの描写。やはり瞳の輝きや座席を覆うビニールの窓のハイライトが美しい。
- Camera: X-H2
- Focal length: 23mm
- Aperture: ƒ/1.4
- Shutter speed: 1/2000s
- ISO: 500
子供を保育園に送ったあとに車道の向かい側にある紫陽花を撮るのが楽しい。
- Camera: X-H2
- Focal length: 33mm
- Aperture: ƒ/1.4
- Shutter speed: 1/2000s
- ISO: 125
近所の商業施設に向かうついでに、小学校のフェンス脇に咲いている額紫陽花。
- Camera: X-H2
- Focal length: 35mm
- Aperture: ƒ/1.4
- Shutter speed: 1/160s
- ISO: 640
カーテン越しの黄昏。
オートフォーカスや動画の撮影性能を考えると、X-H2Sで撮りたい。でも撮れた写真はX-H2のほうが深みがある印象。もちろん、X-H2のフォーカス性能もこれまでのXシリーズと比べて順当に進化したものなので、Xシリーズユーザーが不満に思うことはあまりないのではないかと思えるレベル。
X-H2Sとのコンビが最高だと思ったが、それがお互いの長所短所を際立たせるという、非常に悩ましいコンビである。(こういう経験、前にEOS 5DsRとEOS 5D Mark IVでもした記憶が…)

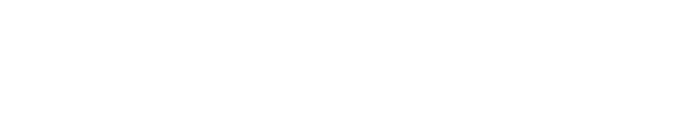























コメント